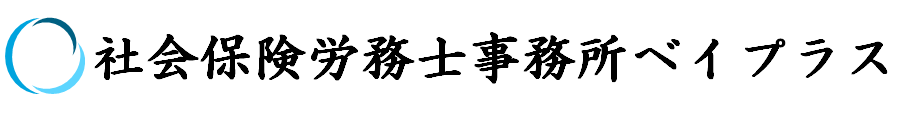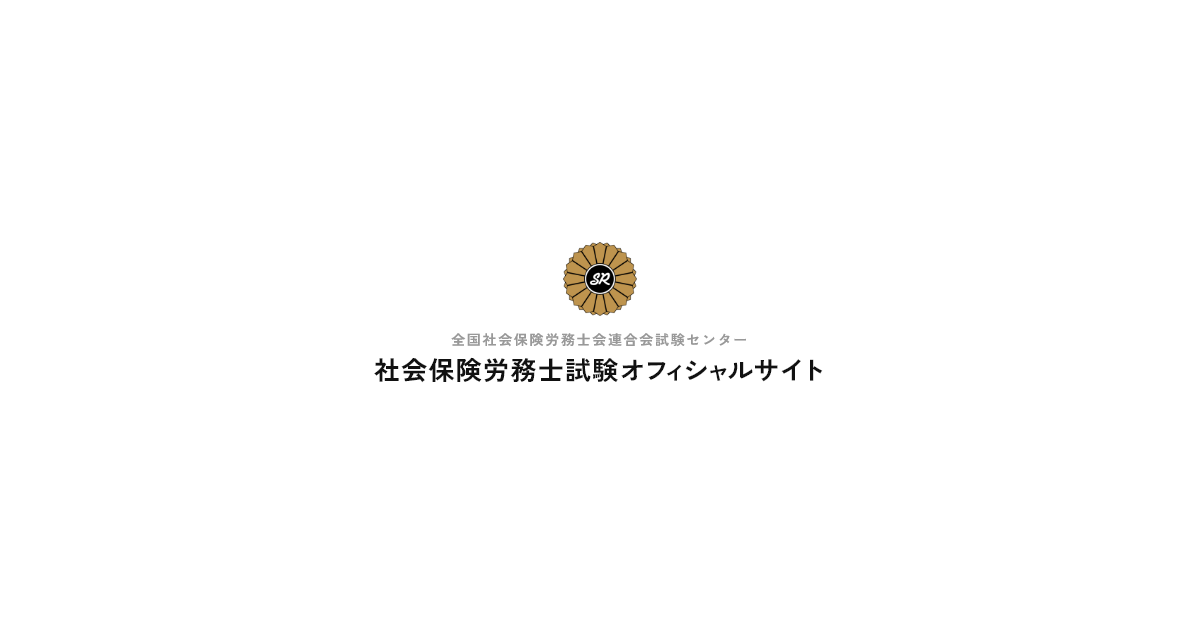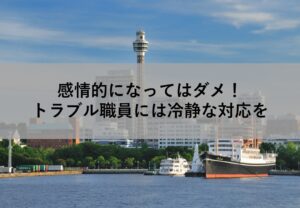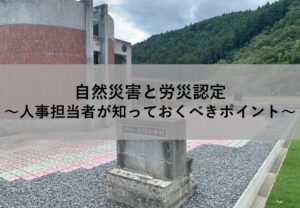社労士試験受験生へ!ステップアップ資格3選
昨日、第57回(令和7年度)社会保険労務士試験が行われました。受験生のみなさま、長時間の戦い、本当にお疲れ様でした。
各予備校から解答速報が出ており、自己採点をされた方も多くいるかと思います。毎年の合格率が6~7%程度ですので、10名中9名は「残念!」と悔しい思いを、1名は「合格」か「解答によっては…」とドキドキしながら結果を待つことでしょう。
※本コラムを執筆している8月25日10時時点では、解答速報を出しているものの、一部の解答が「保留」「検討中」という予備校があります。ギリギリの方は、TAC、大原、クレアールなどいくつか見ておくと良いかもしれません。
さて、合格発表は10月1日(水)で、約1か月あるところですが、ダラダラと過ごしたくないなと感じている方に、次なる目標としておススメしたい資格をご紹介します。
合格確実という方より、来年に向けてまた頑張ろうという方に、社労士試験よりハードルの低い、かつ、社労士試験の勉強を生かせる、人事・労務関連の資格を3つご紹介します。
なぜ別の試験にチャレンジするのか
ひとえに、合格という「達成感」を感じてもらいたいからです。
社労士試験は勉強する範囲が広く、働きながら勉強する社会人にとっては長期間の学習が必要となります。「自分なりに一生懸命勉強してきたのに…」と悔しい思いをしてから、またモチベーションを上げて、社労士試験に向けた勉強を再開するのは容易なことではありません。
そこで、
・社労士試験の学習と試験範囲が重複している
・短期間での合格を目指せる
・人事・労務の仕事にも生かせる
そんな試験にチャレンジして合格することで「達成感」を感じていただきたいと考えています。
【その1】衛生管理者
労働安全衛生法に基づき、事業場の従業員の健康障害を防止し、快適な職場環境を確保するために、一定規模以上の事業場に選任が義務付けられている国家資格です。企業において、安全・衛生管理の専門家として重要な役割を担います。
衛生管理者試験の良い所は頻繁に試験を開催していることです。安全衛生技術試験協会関東センター(東京試験場)では週1~2回試験を行っており、1か月程度先の日程であれば申し込むことができます。
選任の義務
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種に応じて専任の衛生管理者を選任する必要があります。業種によっては、有害な業務があるため、より専門性の高い「第一種衛生管理者」の免許が必要です。
第一種:建設業、製造業、鉱業、農林畜水産業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業などを含むすべての業種
第二種:金融業、サービス業、情報通信業など
第一種では『有害業務』という放射線や化学物質など労働者の健康に悪影響を及ぼす恐れのある業務がある事業所で必要とされます。化学工場(製造業)とIT企業(情報通信業)では、怪我や事故の頻度・重大さに差があります。そのため、有害業務かどうかを基準に、選任できる業種が区別されているわけですね。
※自動車運転免許は第1種が一般人、第2種はタクシーなどの仕事で使う人=上位資格。というイメージがありますが、衛生管理者は逆で、第一種が上位となります。
衛生管理者の主な業務
- 作業環境の管理: 有害物質の測定、換気、照明、温度・湿度の調整など、作業場の環境を適切に保ちます。
- 健康管理: 労働者の健康診断の実施、結果の確認、保健指導、病気の予防などを行います。
- 作業管理: 労働者の作業方法や手順が、安全で衛生的に行われているかをチェックします。
- 衛生教育: 労働者に対し、健康や衛生に関する知識を教え、意識を高めます。
- 健康被害防止対策: 労働災害や職業病が発生しないように、原因究明や再発防止策を立てます。
試験と社労士試験との関連性
衛生管理者の試験は、社労士試験の「労働安全衛生法」と重なる部分が非常に多いです。特に、健康診断、作業環境測定、産業医の設置、ストレスチェックなどの項目は、共通して出題されます。社労士受験で培った知識を活かせるため、効率的に学習を進めることができます。
- 受験資格: 学歴や実務経験に応じて受験資格が定められています。大卒の場合、1年以上の労働衛生の実務経験があれば受験できます。
- 試験形式: 五肢択一式のマークシート方式です。
- 試験科目: 「労働生理」、「労働衛生」、「関係法令」
第二種は有害業務が出題されないため、第二種の試験を受ける際は有害業務について学習する必要がありません。
社労士試験に比べ、出題範囲が絞られているため、短期集中で合格を目指すことが可能です。社労士として、労働安全衛生分野の専門性を高めたい方には最適な資格と言えるでしょう。
医療業であれば第一種が目指してほしいですが・・・
みなさんの仕事で有害業務を扱う、危険度が高い製造業や建設業であれば第一種を取得、デスクワーク中心の情報通信業などであれば第二種を取得、という決め方で良いと思います。
次に、転職を考えるなら第一種を取得しましょう。どの業種・職種であっても衛生管理業務に携われますので。
現在、企業の労働衛生に対する関心は強く、メンタルヘルス対策や健康経営など「労働者の健康と安全」に必要な人材の需要は高まっています。
第一種を取得すれば、業種の選択肢が広がりますし、即戦力となれることをアピールできるため、年収アップやキャリアアップにつながります。
筆者は医療機関で事務員をしておりましたので、第二種を取得するという選択肢はありませんでしたが、有害業務については、普段接しないことが多く、専門知識がありませんでした。また、社労士試験合格後のステップアップとして試験を受けたので、時間もかけることができました。
もし、いきなり第一種衛生管理者を目指すのが不安な場合は、第二種衛生管理者試験から挑戦するのもおすすめです。第二種衛生管理者資格を持っている場合、特例第一種衛生管理者試験を受けると、第一種衛生管理者試験の一部の試験が免除されるので、合格難易度も下がります。
【その2】メンタルヘルス・マネジメント®検定
企業のメンタルヘルス対策における、役割ごとの知識や対処法を習得するための検定試験です。大阪商工会議所が主催しており、労働安全衛生法で定められた「心の健康づくり計画」推進の一環としても注目されています。
コースの概要
この検定には、対象者と目的に応じて主に3つのコースがあります。社労士受験生や人事担当者がステップアップとして挑戦しやすいのは「II種・ラインケアコース」または「III種・セルフケアコース」です。
| コース | ターゲット | 主な目的 |
| I種(マスターコース) | 人事労務部門の担当者、経営者 | 企業のメンタルヘルスケアを企画・推進する能力を養う |
| II種(ラインケアコース) | 管理監督者(管理職) | 部下への適切な配慮、相談対応、職場環境の改善方法を習得する |
| III種(セルフケアコース) | 一般従業員 | ストレスへの気づき、予防、対処法など、自身のセルフケアを習得する |
社労士試験との関連性
社労士試験の「労働安全衛生法」において、ストレスチェック制度や過重労働による健康障害防止対策などが含まれています。メンタルヘルス・マネジメント検定で学ぶ内容は、これらの法的な背景や具体的な対応方法を補完し、より実践的な知識となります。特に、労働者の休職・復職対応や、ハラスメント問題が発生した際の心理的サポートの必要性を深く理解するのに役立ちます。
- 試験との関連性:労働安全衛生法、休職・復職対応、職場環境改善、ハラスメント対策
- 合格までの目安:
- II種(ラインケア):1〜2ヶ月
- III種(セルフケア):数週間(社労士受験生であれば基礎知識があるため、比較的短期間で合格が可能です。)
メンタルヘルス・マネジメントの主な業務(II種ラインケアの知識)
企業においてメンタルヘルス対策を推進する際、管理職(ライン)が中心となって行うべき業務や対応能力を学びます。
ハラスメント予防:パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントがメンタルヘルスに与える影響を理解し、予防策を講じる。
部下の不調への気づきと対応:部下の様子を観察し、変化に気づき、声をかけるスキル。
情報提供と連携:不調者が出た際、産業医や社労士、外部の専門機関(EAP)などへ適切に情報を伝え、連携を取る役割。
職場環境の改善:部下の負担を軽減し、ストレス要因を取り除くための職場内の仕組みづくり。
【その3】給与計算実務能力検定®
労働基準法や所得税法など、給与計算に必要な法律知識と、その実務能力を証明するための検定試験です。職業会計人や社会保険労務士にとって、クライアント企業への給与計算代行や指導を行う上で、不可欠なスキルを証明できます。
検定のレベルと概要
この検定には、2級と1級の2つのレベルがあります。
| レベル | ターゲット | 主な目的 |
| 2級(1ヶ月程度の学習が必要) | 給与計算業務の経験が浅い方、学生など | 給与計算に関する基礎知識と、基本的な計算の実務能力を習得する |
| 1級(2〜3ヶ月程度の学習が必要) | 給与計算業務の経験が豊富な方、管理者など | 年末調整や社会保険料の年度更新など、より高度な実務能力を証明する |
社労士試験との関連性
給与計算実務能力検定は、社労士試験で学習する複数の科目が横断的に関連します。
- 労働基準法:残業代の計算、割増賃金率など。
- 雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法:各種保険料の計算、控除など。
- 所得税法:源泉所得税の計算、年末調整など。
特に2級は、社労士試験の学習で身につけた知識を、具体的な給与計算という実務にどう活かすかを学ぶ良い機会になります。
給与計算実務能力の主な業務
賞与計算:賞与から控除される社会保険料や源泉所得税を計算します。
勤怠情報の集計:労働時間、残業時間、有給休暇の消化日数などを正確に集計します。
社会保険料・税金の計算:健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税などを正しく計算し、控除します。
控除項目の管理:財形貯蓄、社宅費、組合費など、給与から控除する項目を正確に管理します。
年末調整:毎年1回、従業員の所得税を確定させ、過不足を精算します。
来年の試験に向けて、今できること
毎年、多くの受験生が社労士試験に挑み、悔しい思いをしています。1年に1回の試験は、その分、プレッシャーも大きく、モチベーションを維持し続けるのは容易ではありません。
そんなとき、気分転換も兼ねて、比較的短期間で取得できる資格・検定に挑戦してみませんか?
合格という「達成感」は、必ず次の学習へのモチベーションにつながります。
今日ご紹介した資格は、どれも社労士の実務に直結する知識を身につけられるものです。そして何より、合格という「達成感」は、皆さんの自信となり、来年の社労士試験への大きな原動力になるはずです。