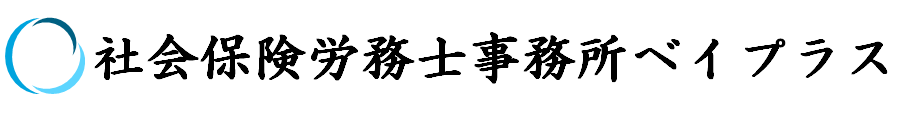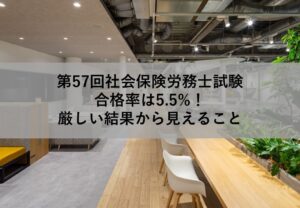健保組合の決算は黒字!でも、喜べない?~健保連の発表から未来の保険料を考える~
先日、健康保険組合連合会(健保連)から「令和6年度(2024年度)の健康保険組合決算見込み」が発表されました。全体で145億円の黒字となり、前年度の1,365億円の赤字から大きく改善しました。
「黒字なら安心だ」「保険料も下がるかも?」と思われるかもしれません。しかし、発表内容を詳しく見ると、決して楽観視できない厳しい現実が浮かび上がってきます。今回は、この発表内容を紐解き、私たちの健康保険の未来、そして保険料がどうなっていくのかを解説します。
健保連とは?
健康保険組合連合会(略称:健保連)は、全国の健康保険組合(約1400組合)を会員として構成される連合組織です。主な目的は、健康保険制度の健全な運営を支援し、国民皆保険を持続可能にするために、政策提言・情報共有・調査研究などを行うことにあります。
医療機関(特に「医事課」と言われる診療報酬請求業務)に従事する方や各健康保険組合の職員の方は、見聞きすることがあるでしょうが、それ以外の方はご存じない方がほとんどかと思います。
💡 健保連の主な役割
1.政策提言
・厚生労働省などに対して、医療保険制度改革や負担の公平化に関する提言を行う。
・「ポスト2025」提言(令和7年)では、高齢者医療の自己負担見直しや公費負担の適正化を提唱。
2.財政・経営分析
・加盟健保の決算を毎年集計・分析(例:2024年度決算見込みでは1,378組合中約48%が赤字)。
・医療費・保険料率・拠出金などの動向をデータとして公表。
3.保健事業・健康づくり支援
・各健保組合と連携し、特定保健指導・生活習慣病予防などの保健事業を支援。
・健診受診率向上やセルフメディケーションの普及啓発。
4.広報・啓発活動
・一般国民に向けて、医療保険制度や財政状況の理解を促す。
・「健康保険のしくみ」などをデジタルブックで公開(kenporen.com)。
5.国や関係機関との調整
・医療費適正化や医療DX(電子化)推進など、関係団体との協議・調整を担う。
なぜ黒字になったのか?要因は「賃上げ」
これまで赤字だったのが、なぜ収支が改善したのでしょうか。
最大の理由は、近年の高い賃金上昇にあります 。
- 保険料収入が大幅に増加
- 健康保険料は、給与や賞与(標準報酬月額・標準賞与額)を基に計算されます。
- 令和6年度は、賃金の上昇(平均総報酬額の増加)だけで2,277億円もの増収効果がありました 。
- これに加えて、保険料率を引き上げた組合もあったため、保険料収入全体では前年度比で4,261億円(+4.9%)もの大幅な増加となりました 。
一方で、支出面では、医療費の伸びが比較的緩やかだったことも黒字化を後押ししました 。
しかし、この黒字はあくまで一時的な追い風によるもの、というのが健保連の見方です。
黒字決算でも潜む「3つの危機」
今回の結果を手放しで喜べない理由は、健康保険組合が構造的に抱える問題が何も解決されていないからです。
危機①:依然として約半数が「赤字組合」
全体では黒字でしたが、内訳を見ると約半数にあたる660の組合(47.9%)が赤字という状況に変わりはありません 。多くの組合が依然として厳しい財政運営を強いられています。
危機②:増え続ける「高齢者医療への拠出金」
現役世代が納める保険料の大きな部分が、75歳以上の高齢者の医療費を支えるための「後期高齢者支援金」などの拠出金に充てられています。
この拠出金は、令和6年度決算で2,065億円(+5.7%)も増加しており、保険料収入の伸び率(+4.9%)を上回っています 。
つまり、賃上げで保険料収入が増えても、それ以上に高齢者医療のための支出が増えているのが実態です。
健保連の資料によると、現役世代の保険料は、自分たちの医療費だけでなく、高齢者医療や介護、さらには子育て支援まで支える構造になっており、その負担は限界に近づいています 。
危機③:「2025年問題」とその先にある未来
2025年には、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となります。これにより、後期高齢者支援金は今後も高い水準で推移することが確実です 。
健保連の試算では、2040年には医療費全体が73兆円に達し(2021年は45兆円)、その半分を後期高齢者の医療費が占めると予測されています 。少子化で現役世代が減り続ける中、今のままでは保険料が20年間で2倍近くまで増加するという厳しい見通しも示されています 。
私たちに何ができるのか?健保連の提言
このような危機的状況を乗り越えるため、健保連は国や国民、そして事業主に対して以下のような提言を行っています 。
- 国への要望
- 高齢者の自己負担割合の見直し(原則3割負担を目指す) 。
- 保険料だけでなく、公費(税金)による負担を増やす構造改革 。
- 医療DXを推進し、重複投薬や検査を減らすなど医療の効率化を進める 。
- 国民へのお願い
- 軽度な不調は市販薬で対応するセルフメディケーションを心がける 。
- 定期的に健診を受け、自身の健康を守る意識を持つ 。
- 事業主へのお願い
- 従業員の健康を守るため、健康保険組合と連携し**「健康経営」**を推進する 。
従業員の健康は経営課題!「健康経営」に取り組むメリット
今回の健保連の提言でも、事業主(企業)と健康保険組合が連携し、従業員の健康づくりに取り組むことの重要性が示されています。その具体的な実践方法が「健康経営」です。
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。従業員の健康を単なる福利厚生(コスト)として捉えるのではなく、企業の生産性や価値向上に繋がる「投資」と位置づける考え方です。(※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です)
経済産業省などが推進する「健康経営優良法人認定制度」を目指すことで、企業は多くのメリットを得ることができます。
1. 企業イメージの向上と人材獲得
認定を受けると、自社のウェブサイトや求人情報に認定ロゴマークを使用できます。「従業員を大切にする会社」という客観的な証明となり、企業のブランドイメージ向上や、優秀な人材の確保・定着(リテンション)に繋がります。
2. 従業員の活力向上と生産性の向上
企業が健康づくりを支援することで、従業員の心身のコンディションが向上します。これにより、仕事へのエンゲージMENTやパフォーマンスが上がり、組織全体の活性化と生産性の向上が期待できます。
3. 社会的な評価と金融機関等からのインセンティブ
近年、投資家が企業の価値を測る上で重視するESG(環境・社会・ガバナンス)の観点からも、健康経営への取り組みは高く評価されます。また、一部の金融機関では、認定法人に対して融資金利の優遇措置などを設けているケースもあります。
まとめ
今回の黒字決算は、賃上げという一時的な要因に支えられたものであり、健康保険制度が抱える構造的な問題はより深刻化しています。今後、「子ども・子育て支援金制度」の開始も予定されており 、現役世代の負担はさらに増すことが予想されます。
経営者の皆様におかれましては、自社が加入する健康保険組合の財政状況に関心を持っていただくとともに、従業員の健康増進が医療費の適正化、ひいては将来の保険料負担の抑制に繋がるという視点から、より一層の「健康経営」への取り組みをご検討いただければと思います。
毎月の保険料を見直したい、健康経営に興味があるけど取り組めるかわからない、などのお困りごとは、ぜひ社会保険労務士事務所ベイプラスにお問い合わせください。