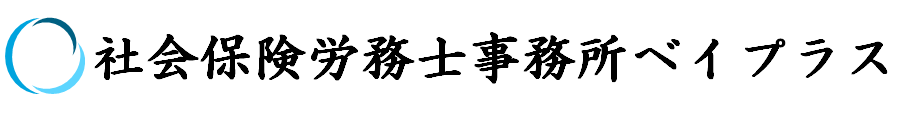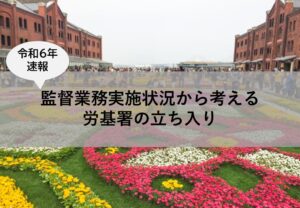自然災害と労災認定~人事担当者が知っておくべきポイント~
医療機関での労災といえば、業務中の針刺し事故があり、ちょっとした不注意による場合が多くある印象です。新型コロナウイルス感染症が蔓延していたときは、患者からの罹患による労災申請も多くありました。因果関係を示すために発症前1~2週間の行動履歴、患者接触状況などの資料を提出していました。
人事担当者の多くは、一般的な労災に対応した経験があると思いますが、自然災害での労災認定を考えている方はあまり多くはないでしょう。
ご存知のとおり、日本は地震や台風など自然災害の多い国です。職場で勤務中に災害に遭遇した場合、それは労災保険の対象となるのか?と疑問に思う方も多いでしょう。
労災保険では「業務上災害」または「通勤災害」に該当する場合に補償されます。自然災害が原因であっても、業務や通勤と災害との因果関係が認められれば労災として扱われます。逆に、業務とは関係のない偶然の災害であれば、原則として労災認定は困難です。
自然災害でも労災になるの?
地震や台風などの自然災害は「不可抗力だから労災にならない」と誤解されることがあります。
しかし実際には、業務との関連性があれば労災補償の対象です。
例えば勤務中に地震で社屋が倒壊した、台風の中で顧客先に移動していた、通勤途中で水害に巻き込まれた──こうした場合は労災保険の適用が検討されます。
業務災害
業務遂行中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものとして業務災害として差し支えない。
通勤災害
業務災害と同様、通勤途中で津波や建物の倒壊等により被災した場合にあっては、通勤に通常伴う危険が現実化したものとして通勤災害として差し支えない。
人事が直面する「よくあるケース」
地震発生時に、労災が認められた実例を紹介します。業務中の災害と通勤中の災害は、それぞれどのような条件で労災と認められるのかを確認しましょう。
業務災害のケース
- 仕事中に地震や津波に見舞われ、怪我や死亡につながった事例
- 出張先の地域で地震や津波の被害に遭った事例
- 仕事の休憩時間中に地震や津波の被害にあった事例
通勤災害のケース
- 自宅ではなく避難所から会社への通勤中に怪我をした事例
- 帰宅中に警報が発令され、自宅ではなく避難所に向かう最中で怪我をした事例
- 地震の影響で交通機関が止まり、長時間の徒歩帰宅中に怪我をした事例
これらのケースは、すべて労災として認められます。
業務災害として認められるには、地震や津波が危険な状況下で仕事をしていたという条件が求められます。つまり、仕事中や休憩中の事故は、労災の認定が可能です。また、出張には業務命令が伴うため、出張先での被災も労災に含まれます。
通勤災害の認定条件は「住居」と会社を行き来することです。自宅が利用できないとき、避難所は一時的な住居として認められます。通勤の移動手段は、災害時の交通状況によって臨機応変に判断されます。
東日本大震災による大川小学校の教訓
宮城県にある石巻市立大川小学校では、大震災後の津波により児童108名中74名・教員10名が亡くなりました。海からは3.7km内陸に位置しており、津波は到達しないと思われていましたが、未曽有の地震による大津波は川を遡上し、15時37分ごろ、大川小から避難する児童らを前面から津波が襲ったのです。
14時46分の地震発生後、15時には大津波警報が発令され町が避難を呼びかける中、50分間校庭にとどまり続けたこと、二次避難先が想定しておらずその場で議論を行ったこと、結果的に高い裏山ではなく「橋のたもとの小高い場所」への避難を決めたことなど、事前事後の不適切な対応を含め、多数の問題が明らかになっています。



宮城県内には東日本大震災の教訓を伝えるべく、『震災遺構』が多く存在します。震災前の大川小学校と地域の関わりや、震災後現在までにたどった経緯、教訓とすべき防災について学ぶこと、実際に周辺の地形や川までの道のりを歩いて見学し、当時を振り返り適切な避難行動について考えることは、防災を考えるうえで非常大切なことでしょう。
人事担当者が準備すべきこと
労災の発生を低減するため、何より大切な従業員を守るためにも、地震の発生に備えた事前準備は、企業にとって不可欠です。人事部門が主導してできることは次のとおりです。
BCP(事業継続計画)の策定や安否確認システムの整備(メール、チャット、専用アプリなど)
BCPの策定によって、災害時における事業と従業員の安全確保が可能です。BCPは「事業継続計画」の略称で、災害やシステム障害など、事業の継続に脅威を与える緊急事態の発生に備えた方針を意味します。
地震が発生して社屋や従業員に被害が及ぶと、事業の継続は困難に陥ります。BCPを事前に策定し、従業員の安全を考慮した計画を立てておくことで、従業員を守りながら事業を早期復旧させることができます。
安否確認システムは、あらかじめ登録した定型文のメッセージを従業員に向けて自動で配信できるシステムです。災害発生時には従業員の安否確認が重要になります。安否確認システムを導入することで、従業員に怪我はないか、危険な状況でないか迅速に把握することができます。
BCPの策定もあわせて行うことで、従業員は緊急時でもよりスムーズな判断のもとで行動できるでしょう。
防災訓練や避難経路の周知を定期的に行う
防災訓練を実施すると、従業員が地震発生時の適切な行動を知ることができ、怪我や事故に遭うリスクを減らすことができます。
企業全体で実施する避難訓練では、地震の発生を想定し、正しい経路で安全な場所まで避難をする経験を積むことが重要です。災害時の避難方法が曖昧な場合、危険な場所に留まり続けるリスクや、行動を焦って転倒し怪我を負うリスクが発生します。避難訓練を通じて災害時の行動を明確にすることで、緊急事態が発生した際にも安全な避難ができます。
人事担当者には就業規則の整備や休暇制度の新設が求めれる
一般的な企業向け防災対策では、BCP策定や訓練の実施がメインですが、人事担当者にはさらなる準備が求められます。
もっとも必要なことは就業規則やマニュアルに災害時の勤務・休業ルールを明記することです。休日や深夜に自然災害が発生した場合、出勤させるのか、出勤させてはいけないのか、正社員とパートタイマーでは雇用契約が異なり、強制的な指示・命令ができないことも考えられます。
また、勤務先に被害が無くても、従業員の自宅、実家などへの被害により通常通りの勤務ができないこともあります。保育施設が通常通りの運営ができず子どもを預けられないなんてこともあるでしょう。そうした従業員をサポートするためには「災害休暇などの特別休暇」の制度設計も必要かもしれません。
災害時の労災対応チェックリスト(人事担当者用)
- 就業規則に「自然災害時の勤務・休業」のルールが明記されているか
- 災害発生時に 出社命令を出す基準 が整理されているか
- 従業員の 安否確認手段(電話網・メール・チャット・専用アプリ等)が確保されているか
- 労災申請の 手続きフロー(必要書類・証明者・提出先) が明文化されているか
- 通勤災害と業務災害の違いを担当者が理解しているか
- 災害休暇・特別休暇の制度が整備されているか
- 防災訓練・避難経路周知を 定期的に実施・記録 しているか
- 建物・社屋の 安全点検・備蓄品の確認 を人事・総務と連携して行っているか
- 災害対応に関する連絡先(労働基準監督署・社労士・顧問弁護士等)が整理されているか
- 災害発生後の 記録保存(発生状況・勤務実態・写真・日報) を取る体制があるか
守れる命を守るために
自然災害はいつ、どこで起きるか分かりません。災害そのものを防ぐことはできません。
「想定外だから仕方がない」と言われることが多い自然災害ですが、実際には多くのケースで 人々の判断や準備次第で結果が変わるのです。
人事担当者が 平時に仕組みを整えておくことが、従業員と企業を守る最大の備えになります。
どうか明日からでも、チェックリストのひとつでも取り組んでみてください。
それが、災害時に従業員から「守られている」と思ってもらえる、最初の一歩になります。
就業規則の作成、見直しや医療機関における災害への備えについては、社会保険労務士事務所ベイプラスにお気軽にお問い合わせください。