人事1年目のための就業規則の基本とよくある従業員からの質問
「就業規則って、読むものなんですか?」
配属されたばかりの人事部。
上司に言われて初めて「就業規則」を開いたけれど、正直ピンとこない。
「これ、本当に誰か読んでるの?」――そんなふうに思ったことはありませんか?
でも、少しずつ仕事を覚えていくうちに気づくはずです。
・「育児休業って何日まで取れるんですか?」
・「副業ってOKなんでしょうか?」
・「遅刻や無断欠勤に、どんなルールがありますか?」
・・・従業員からの質問に答えるとき、いつも頼りになるのが就業規則なのです。
実は就業規則は、ただの「お作法集」ではありません。
会社で働く人すべてに関わる、ルールと安心のよりどころ。
知らないと困る場面も多く、人事としての信頼感を高めるには欠かせない知識です。
このコラムでは、人事1年目でもわかる「就業規則の基本」について、押さえておきたいポイントをやさしく解説していきます。
「難しそう」と思っていた人も、きっとスッキリ理解できるはず。
明日からの対応に自信が持てるようになる、そんなきっかけになりますように。
就業規則の目的とは?
就業規則は、会社と労働者の間の「労働条件」や「職場のルール」を明文化したものであり、主に次のような目的で作成されます。
●労働条件の明確化
賃金、労働時間、休暇など、社員の働く条件を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐ。
●社内秩序の維持と公正な運用
勤務態度や懲戒のルールを定めることで、社員全体に公平なルールを適用できる。
無秩序や不公正を避ける。
●トラブル発生時の根拠
解雇、懲戒などの対応の際に、法的根拠・手続きの妥当性を示す重要資料となる。
●従業員の納得感・信頼形成
明文化されたルールによって、従業員は安心して働ける。
(10名以上の従業員を使用する事業場の場合)
就業規則がないこと自体が労働基準法違反となり、罰則が科され社会的な信頼を損なう可能性があります。
作成・届出の義務
10人以上の労働者を常時使用している事業場は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法89条)。
・複数の事業場がある場合は、1事業場あたりの人数で数えます
・正社員に限らず、アルバイト従業員なども労働者として数に含めます
「従業員が8人しかいないから就業規則は作らなくて良いね」とおっしゃる経営者の方がいます。
上記のとおり作成の義務はありませんが、「従業員が少ないから作らない」あるいは「従業員が増えたから慌てて作る」のはおすすめできません。
人数が少なくても組織で働くうえではルールが必要ですし、明文化されていなければ労務トラブルにもなります。人数が少なく、まだまだ安定しない時期だからこそ、就業規則を作成することで「将来働きやすい職場」を考える機会にしていただきたいと思います。
就業規則の届出は電子申請や郵送で行うことができるため、労働基準監督署に足を運ぶことは少なくなってきましたが、それでも対面での提出が必要な場合もあります。
弊所は横浜市中区にあるため、横浜南労働基準監督署(みなとみらい線馬車道駅)が管轄ですが、隣の横浜市西区は横浜北労働基準監督署(新横浜駅)が管轄になります。
管轄の労働基準監督署は「どこにあるのかな~」と一度確認しておくとよいでしょう。
就業規則で定めるべきこと
絶対的必要記載事項(就業規則に必ず記載すべき事項)
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の有無と内容
→ 勤務時間・休日体系の基本 - 賃金(計算・支払い方法、締切日と支払日、昇給)
→ 給与や手当の支払いルール - 退職(定年、解雇、解雇の事由を含む)
→ 自己都合・会社都合の対応
いずれも働くうえで非常なルールですね。基本中の基本となる就業規則の柱ですので確実に押さえておきましょう。
相対的必要記載事項(事業場に定めがある場合に記載すべき事項)
- 臨時の賃金(賞与)、食事・作業用品の負担
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償・業務外の傷病手当
- 表彰・制裁
- その他、全従業員に適用される規定
よくある従業員からの質問と対応例
従業員からの質問は様々あり、就業規則に定めていないことを聞かれることもあります。
「おそらく大丈夫です」と曖昧な回答、あるいは間違った回答をすると、後々従業員とトラブルになります。
従業員からすると、「人事担当者に確認した」「人事がOKした」の一点張りで、お互い嫌な思いをする結果になりますので、すぐに回答できない場合は、「このあと確認して、メールします」と回答を保留にしましょう。
「よくある質問と回答集」をこれまでの人事担当者が作っておいてくれれば、新人でも対応できることもありますが、そんなに都合よくはいかないものです。
ここでは、従業員からよくある質問と対応例をいくつかピックアップしましたので、『自分ならこう答える』とご自身の会社に置きかけて考えてみてください。
- 「体調不良でしばらく休みたいのですが…」
→ 休職制度の対象条件や期間、復職のルールを案内。 - 「子どもが生まれるので育休を取りたいです」
→ 育児休業規程の該当条文を示し、社内手続きや制度の概要を説明。 - 「有休は好きな日に全部使えるのですか?」
→ 時季変更権や繁忙期の考慮など、会社側の運用ルールも併せて案内。 - 「忌引休暇って何親等までですか?」
→ 慶弔休暇の社内ルールを明記し、具体例で説明。 - 「SNSで社名を出してもいい?」
→ SNSガイドラインや服務規律を根拠に、会社の信用保持義務を伝えます。 - 「副業してもいいですか?」
→ 副業の可否や申請方法は就業規則で定めておく必要があります。 - 「退職の申し出はメールでもOKですか?」
→ 就業規則で定めた手続き(書面・口頭等)に基づいて案内。 - 「解雇された場合はどうなりますか?」
→ 解雇事由や手続きは明確に就業規則へ記載し、本人に説明。 - 「退職したらすぐに再就職してもいいですか?」
→ 競業避止義務があるか、誓約書の有無なども含め確認・説明。 - 「退職後の健康保険はどうなりますか?」
→ 社会保険の任意継続制度や国保切替の概要を伝える。 - 「出張先で事故に遭いました」
→ 業務災害か否かの判断、報告ルート、労災保険の案内などを説明。 - 「給与明細に控除額が多すぎる気がする」
→ 控除内容の根拠(社会保険料・住民税・社内貸付など)を明確に回答。 - 「始業時間の30分前に来るように言われたのですが?」
→ 業務命令としての合理性や、早出勤務の取り扱いを説明。
ハラスメントや退職など“労務トラブル”になりそうな事案はすぐに報告を
挙げればキリがなく、人事に対する質問は多岐にわたります。
数をこなしているうちにある程度の質問には答えられるようになりますが、「ハラスメントを受けた」「退職したいと考えている」などの内容は非常に重要な事案です。
そんなときは、すぐに上司に報告をしましょう。労務トラブルになりそうか、あるいはすでにトラブルが具体化しているか、動き出すきっかけになります。
“使える就業規則”にするために
定期的な見直しは必要?
就業規則は一度作って終わりではありません。
法改正や会社の実情に応じて、定期的な見直しが不可欠です。
たとえば、育児・介護休業法の改正や労働時間制度の見直しなど、ここ数年でも企業に求められる対応は大きく変化しています。
就業規則が古いままだと、実態とのズレが生じ、トラブルの原因になることも。
目安としては年1回、少なくとも法改正があった際には、内容をチェックすることが望ましいでしょう。
現場とのすり合わせ・周知義務
就業規則は、法的には「労働者に周知されてはじめて効力を持つ」とされています(労働基準法 第106条)。
したがって、作成や改定の際には、現場の意見を取り入れながら作成・改定し、完成後にはしっかりと説明し、従業員に伝えることが大切です。
説明会の開催、イントラネット掲載、メールでの配布、書面交付など、会社に合った方法でわかりやすく周知しましょう。
『社長の机の引き出しや金庫にしまってある』は従業員がいつでも閲覧できる状況ではないので、NGです。
別規程との整合性(例:賃金規程、育児介護規程など)
就業規則本体だけでなく、賃金規程・育児介護規程・出張規程などの「付属規程」との整合性も重要です。
たとえば就業規則に「フレックスタイム制を導入する」と記載していても、賃金規程でその勤務体系に対応していない場合、トラブルが生じる可能性があります。
変更時は関連規程もセットで確認し、矛盾がないように管理することが求められます。
社会保険労務士と相談するタイミング
就業規則は法律文書であると同時に、会社の方針や文化を反映する「会社の憲法」のような存在です。
制度変更、トラブル対応、法改正への対応など、判断が難しい局面では社会保険労務士に相談することをおすすめします。
特に以下のようなときには、社労士との連携が効果的です。
- 法改正(例:労働時間制度、育児・介護休業法など)の影響があるとき
- 新たな勤務制度や人事制度を導入するとき
- 労使トラブルへの備えを強化したいとき
- 就業規則がしばらく見直されていないとき
社労士は、法的観点だけでなく、現場に即した実務運用やリスク回避策までサポートできます。
早めの相談が、職場の安心と信頼につながります。
お気軽に社会保険労務士事務所ベイプラスまでご相談ください。
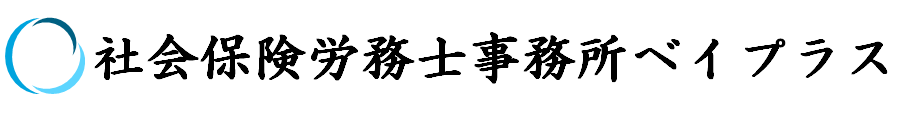
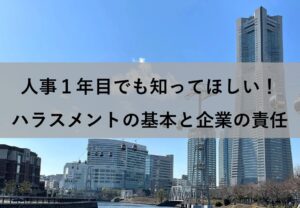

“人事1年目のための就業規則の基本とよくある従業員からの質問” に対して1件のコメントがあります。