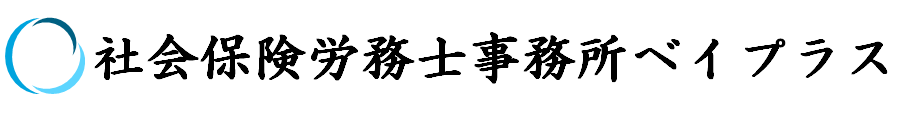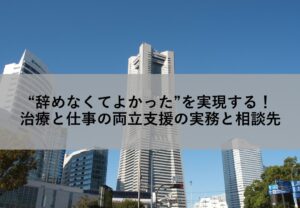未経験でも安心!人事初心者が知っておくべき法律と資格
はじめて人事・労務の担当者になった方や新人教育に悩んでいる人事責任者に読んでいただきたいテーマです。
「営業部にいました○○です。この春から人事部に異動になりました。よろしくお願いします!」と、人事異動のあった会社は多いのではないでしょうか。
営業であれば自動車の運転が必須の場合もありますが、人事・労務の仕事に必須の資格は特にありません。
「人事部に配属されたけれど、何から始めればいいのか分からない…」
「法律って難しそうだし、資格も取らないとダメ?」
そんな不安を抱えている人事担当者の方へ。
人事の仕事は、採用から労務管理、制度設計、退職対応まで実に幅広い分野に関わります。だからこそ、最初は「基本の法律」と「実務に役立つ資格」から押さえることが大切です。
このコラムでは、未経験の人でも安心してスタートできるように、「人事担当者がまず知っておきたい法律」と「おすすめ資格」をやさしく解説します。
人事部門はやることがいっぱい
人事部門の仕事は「採用」だけではありません。
従業員の雇用契約、給与計算、社会保険手続き、就業規則の整備、人事評価、教育・研修制度の企画など、実に様々です。
また、それぞれの作業には守るべき法律が存在するため、人事部門が知っておくべき法律は多岐にわたります。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法など・・・。
これらは人事部門が扱う業務において重要な法律といえますが、いきなりすべてを網羅的に理解するのは非常に難しいことでしょう。
人事担当者が最初に知っておきたい法律3選
① 労働基準法(ろうどうきじゅんほう)
人事・労務の土台となる法律です。「労基法」なんて略称で聞いたことがあるかもしれません。
労働時間、残業、休日、有給休暇など、従業員の働き方に関する基本ルールが書かれています。
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法は会社(経営者)と従業員が守るべき最低限のルールが定めらています。
この法律ができたのは戦後まもないときで、会社の経営者の力は強く、従業員は弱い立場にありました。1日8時間を超える労働、非常に安い賃金、危険な環境での作業といったことが当たり前でしたので、「労働者を保護する」ために作られたのが労働基準法です。
人事担当者においては、最も大切な基礎になる法律です。
② 労働契約法(ろうどうけいやくほう)
「雇用契約ってどんな内容にすればいいの?」という疑問に答えてくれる法律です。
労働条件の明示、雇止め、解雇、懲戒など、雇用トラブルを防ぐためのルールが定められています。
もともと、雇用に関する多くのルールは、労働基準法だけでなく、長年の判例(裁判例)によって形成されてきたルール=判例法理がもとになっています。
労働契約法は、そうした判例の内容を条文化し、「会社と社員の間にどんなルールがあるべきか」を明確にしたものです。
③ 労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)
働く人の健康や安全を守るための法律です。
職場のお手洗いは清掃されて、清潔ですか?事務室内の空調や照明の明るさは適切ですか?
あまり考えたことないことかもしれませんが、快適な職場環境をつくるために守るべきルールが定められています。
人事担当者の業務に、ストレスチェックなどメンタルヘルス対策などもあり、近年、その重要性が増しています。
「メンタル不調の兆しに気づける人事担当者」は、現場から信頼されやすくなります。
ネットで調べる前に、はじめに手に取っていただきたい
働き方のルール~労働基準法のあらまし~(東京労働局)
こちらは東京労働局が作成しているパンフレットで、労働基準法の基本をまとめた1冊になっています。
人事担当者は、はじめに見ていただきたい資料です。
新人教育で悩まれている人事責任者のみなさま
まずはこちらのパンフレットをテキストとして、新人へのレクチャーをしてはいかがでしょうか。
筆者自身、このパンフレットを使用して、新人(新卒・既卒)に1コマ60分×4回のレクチャーを行いました。
もし、ご自身の職場でフレックスタイム制があれば、事例を交えて説明していただくことも良いでしょう。
「人事・労務」の実務がまるごとわかる本(日本実業出版社)
次は書籍です。人事・労務に関する仕事の全体像を掴むには非常に分かりやすくまとまっています。
社会保険の手続き、給与計算の実務の基礎、労務管理の概要がまとまっています。
(筆者が人事部門に異動になった際にはじめて購入した書籍です)
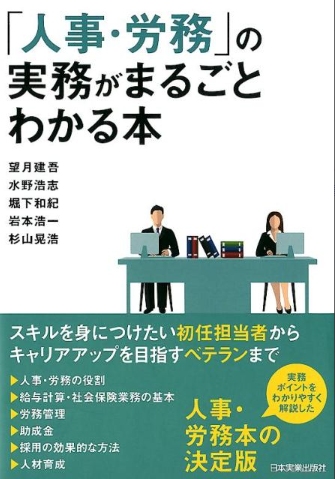
人事初心者におすすめの資格・検定3選
| 衛生管理者(第2種) | 50人以上の職場では必須。試験対策が明確で取り組みやすい | https://www.exam.or.jp/ |
| 給与計算実務能力検定(2級) | 給与計算・社会保険の基礎を学べる。実務直結型 | https://jitsumu-up.jp/ |
| メンタルヘルスマネジメント検定(Ⅱ・Ⅲ種) | 職場の心の健康管理。新人・中堅に人気の民間資格 | https://www.mental-health.ne.jp/ |
いずれの試験も労働基準法の基礎が出題され、これらの勉強を通じて全体を理解することにつながります。
特に衛生管理者は50人以上の事業場では選任が義務付けられているため、「資格手当」を設けて取得を推進している企業もあります。
衛生管理者は毎月数回実施しているため、いつでも始められる、挑戦できる点もおススメするポイントです。
注:第2種衛生管理者免許は金融業、サービス業、情報通信業などで選任できます。ご自身の会社が建設業、製造業、医療業などの場合は第1種衛生管理者免許が必要です。
いきなり「社会保険労務士」を目指す!は・・・
労働・社会保険の法律に関する専門家である『社会保険労務士』を目指すことは非常に素晴らしいことです。
しかし、人事に配属された新人がいきなり挑戦するのは、あまりおススメしません。
社会保険労務士試験の出題範囲は、「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「健康保険法」「国民年金法」「厚生年金保険法」その他多数の法律と非常に多岐にわたり、勉強する期間も長くなります(試験は年1回)。
社会人として働きながら、1回で合格する方は非常にまれで、平均3~4回ともいわれています。
迷ったら“社労士に相談”という選択肢も
人事は、「経験がすべて」ではありません。
正しい知識をもとに、法律や制度に沿って対応することが信頼される人事への第一歩です。
もし「自社に合った制度が分からない」「就業規則を整備したい」「助成金も気になる」というときは、社会保険労務士(社労士)に相談することで、実務の視点から的確なアドバイスが得られます。
社会保険労務士事務所ベイプラスでは、
新人・若手人事担当者向けに、制度整備のアドバイスや相談窓口の支援も行っています。
「ひとりで悩まず、専門家に聞く」選択肢、ぜひご活用ください。