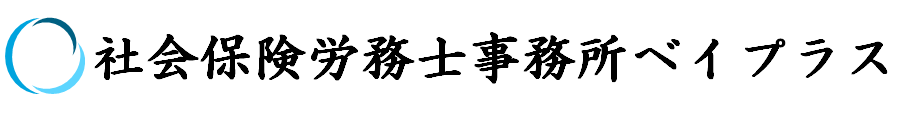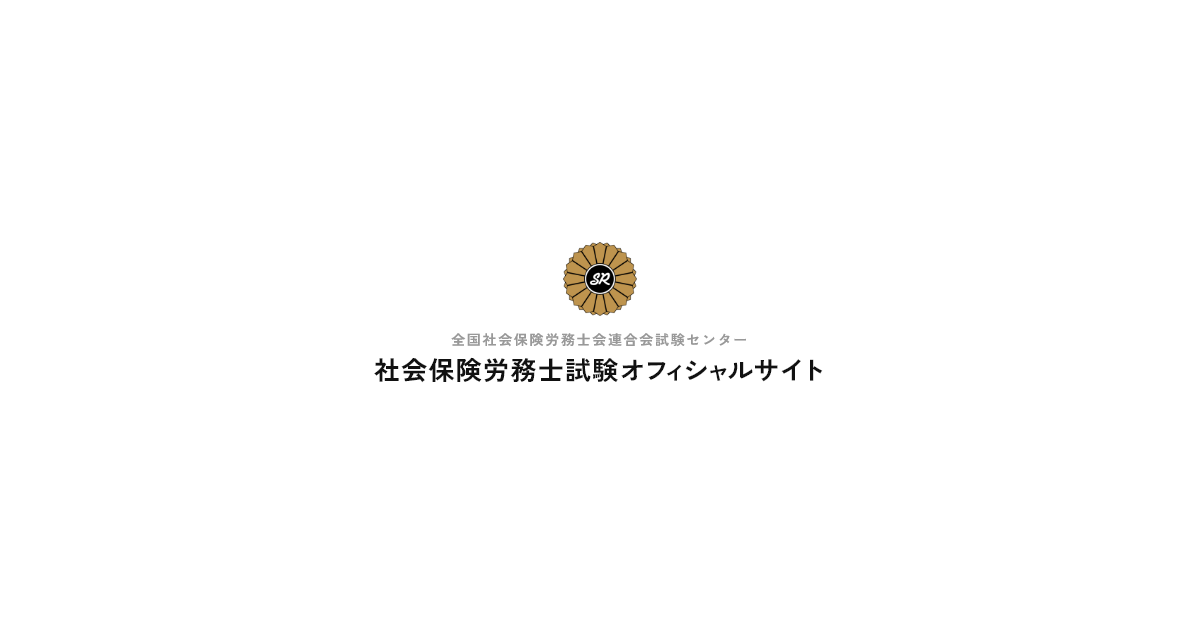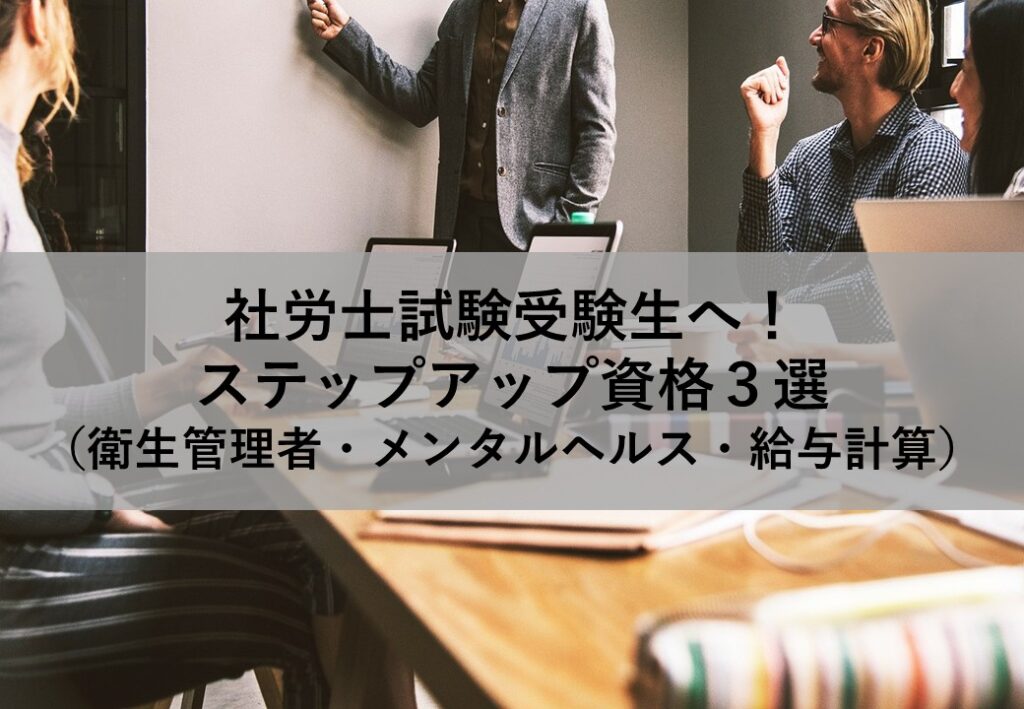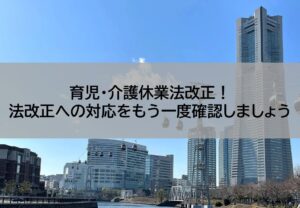第57回社会保険労務士試験 合格率は5.5%!厳しい結果から見えること
去る10月1日、厚生労働省から第57回社会保険労務士試験の合格者が発表されました 。夏の終わりに全国で試験に挑まれた受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。
まずは、見事合格を果たされた皆様、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。一方で、残念ながら今回は力が及ばなかった方も多くいらっしゃったかと存じます。皆様のこれまでの努力に、深く敬意を表します。
今回の試験結果は、合格率5.5%と、昨年の6.9%から1.4ポイント低下する厳しいものとなりました 。今回はこの試験結果を紐解きながら、その内容と、これからの社労士の役割について考えてみたいと思います。
合格率は5.5%!20人に1人しか受からないという現実。
「20人に1人ということは、この列で受かるのは自分だけだな!!」という試験前の入れ込み?暗示?
試験会場によって異なりますが、私が受けた時の話です。令和4年に受験したのは神奈川県内の某大学、100名~150名くらいの教室だったと思います。1列20名くらいでしたので、「この列で受かるのは1名。。。自分だな!」と試験前の待ち時間に考えていました。よく考えるとなかなか高いハードルですよね。
社労士試験は誰でも受験できるという類のものではなく、多くの場合、大学卒業、一定の実務経験がある人が受験しています。TACや大原などの予備校に時間とお金をかけて挑んでいる方が大半でしょう。にもかかわらず、20人に1人とは。
特に午後の択一式試験は時間との闘い。焦りは禁物。なので、「この列で受かるのは1名。。。自分だな!」と暗示。
それくらい落ち着いていたほうが、いろいろ冷静に見れるものです。
試験結果の概要
まずは、発表された主要な数値を見ていきましょう。
- 受験者数:43,421人 (前年 43,174人)
- 合格者数:2,376人 (前年 2,974人)
- 合格率 :5.5% (前年 6.9%)
受験者数は昨年から微増しましたが、合格者数は約600人減少し、合格率は5%台という狭き門となりました 。この数字からも、今年の試験の難易度の高さがうかがえます。
合格者のプロフィールは?
次に、どのような方々が合格を勝ち取ったのか、その顔ぶれを見てみましょう。
- 年齢別:最も多いのは30歳代 (32.5%)、次いで40歳代 (27.5%)と、働き盛りの世代が合格者の6割を占めています 。なお、最年少は19歳、最高齢は78歳と、幅広い世代の方が挑戦し、見事合格されています 。
- 職業別:会社員が58.4%と半数以上を占めており、多くの方が働きながら難関を突破されていることがわかります 。次いで公務員 (11.7%)、無職 (11.0%) となっています 。
- 男女別:男性が60.3%、女性が39.7%という構成でした 。
社労士として登録し、支部会や研修会に参加すると分かりますが、他の士業と比べて女性が多い。グループディスカッションなどでも男女半々が当たり前です。
個人的にはすごく良いことだと思います。
合格から「社会保険労務士」になるまで
社会保険労務士は、試験に合格しただけですぐに名乗れるわけではありません。
合格後、原則として2年以上の実務経験があるか、または実務経験のない方は事務指定講習を修了する必要があります 。これらの要件を満たした上で、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録することで、晴れて「社会保険労務士」としてのキャリアがスタートします 。
他の士業との違いとして、「開業」・「勤務」と働き方(勤務先)によって登録の区分があることです。
※区分が違うからと言って「社会保険労務士」に違いはありません。
入会金、年会費などは所属する都道府県会によって多少の違いはありますが、私の所属する神奈川県社会保険労務士会は以下の通りです。
| 収入印紙 | 30,000円 |
| 登録手数料 | 30,000円 |
| 入会金 | 開業70,000円 / 勤務40,000円 |
| 年会費 | 開業90,000円 / 勤務45,000円 |
次のステップとして・・・各科目の知識を厚くする
次のステップをお考えの方や来年もチャレンジする予定の方に、私が社労士合格後に取り組んだ資格・試験についてお伝えします。
労基法、安衛法、年金科目などの「知識を厚くする」ために、以下の資格・試験はいかがでしょうか。
| 特定社会保険労務士(特別研修→紛争解決手続代理業務試験) 労働基準法・労働契約法を厚く | 社労士として登録後にチャレンジできます。 通常の社会保険労務士の業務に加えて、個別労働関係の紛争解決手続代理業務を行うことができる専門家です。研修と国家試験に合格し名簿に付記を受けることで、裁判外での円満解決を目指し、労働者や事業主の代理人として紛争解決の場に立ち、交渉や和解契約の締結を代行します |
| 高度年金・将来設計コンサルタント 厚生年金保険法・国民年金法を厚く | 社労士として登録後にチャレンジできます。 公的年金制度及びその周辺知識に関する研修(理論編・実践編)を実施し、修了者に公的年金制度及び私的年金制度等の専門的知識を基に、将来生活設計全般にあたっての助言を行うことができます。 ファイナンシャルプランナーをお持ちの方は相性が良いです |
| 衛生管理者(第一種・第二種) おすすめ!! 労働安全衛生法を厚く | 衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられている国家資格です。労働者の健康障害や労働災害を防止するための専門家であり、社労士業務との相乗効果が非常に高いのが特徴です。 |
| 給与計算実務検定 労働基準法を実務で使えるように | これまでの勉強を厚くするとは少々異なりますが、複雑な給与計算に関する実務能力を証明する民間資格です。労働社会保険料や税金の計算、関連法規の知識など、給与計算に必要なスキルを体系的に学ぶことができます。 |
| 健康経営アドバイザー ますます重要視される「従業員の健康」を考える | 健康経営の必要性を伝え、自社内の健康経営への取り組みに必要な情報を提供し、健康経営の実践へのきっかけを作る普及・推進者です。アドバイザーは、従業員の健康状態や職場環境のモニタリングを行い、健康経営プログラムの効果を分析し、必要に応じて改善策を提案します。 |
次のステップどうしよう?とお考えの方、紹介した中では、短期間の勉強で、毎月試験を実施している「衛生管理者」をお勧めします。
過去のコラムもあわせてご覧ください。
これからのステップに悩んでいる方はご相談ください
今回の試験結果は、合格率5.5%という大変厳しいものでした 。これは、社会保険労務士という国家資格が、それだけ高度で専門的な知識を要求されることの表れでもあります。私たち現役の社労士も、この結果に身が引き締まる思いです。
また、ご自身の興味や、将来どのような社労士になりたいかというビジョンに合わせて、次のステップを選んでみてはいかがでしょうか。自己投資を続け、専門性を磨こうとするその姿勢こそが、これからの社労士にとって最も大切なことだと思います。
そして、今回惜しくも合格に至らなかった皆様、これまで学習で培った知識や経験は、決して無駄にはなりません。ぜひご自身のキャリアの糧としてください。
もし、「来年も受けようかな?無理かな?」とチャレンジを悩まれているか方、よろしければ社会保険労務士事務所ベイプラスまでご相談ください。お待ちしております。