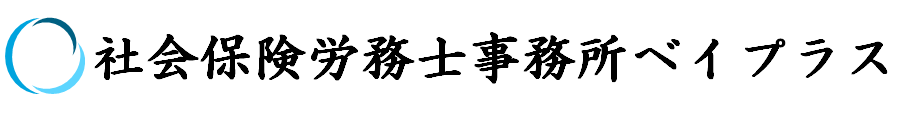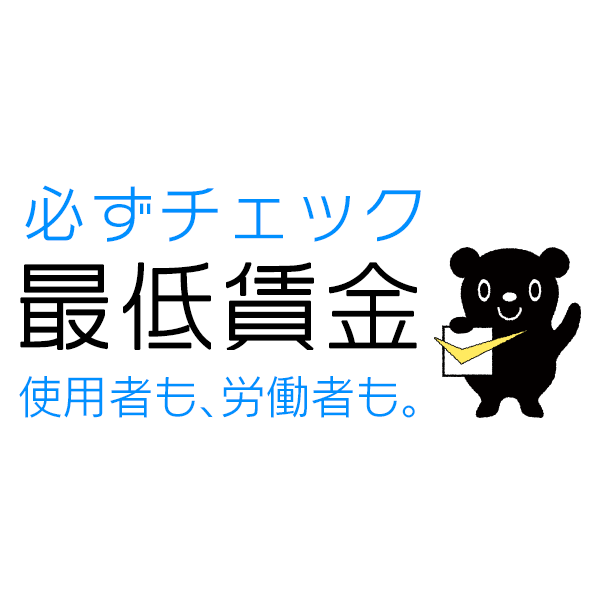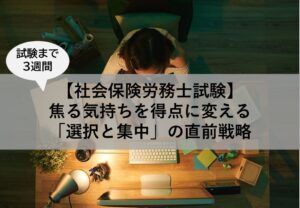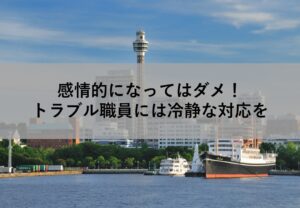毎年確認!最低賃金を下回っている従業員はいませんか??
毎年7月下旬~8月上旬にかけて発表されるのが最低賃金の改定です。一時間当たりの賃金(時給)の最低ラインをいくらにするか、厚生労働省の審議会で全国的な目安を決め、各都道府県における金額を地方最低賃金審査会で具体的に決定します。東京が全国1位の高水準で、神奈川県は1円低い2位というのが、例年のあり方です。
さて、神奈川地方最低賃金審議会は8月8日、県内の最低賃金を現行の1162円から1225円に63円引き上げるよう、神奈川労働局長に答申しました。5.4%の引き上げ幅は、時給換算された2002年以降で最大、この金額は10月4日から適用される見通しです。
引き上げ額は、厚生労働省の中央最低賃金審議会が8月4日に決めた目安と同額であり、物価高に対応し、引き上げ幅は最大だった前年の50円(4.49%)をさらに上回る結果になりました。
今回のコラムでは、最低賃金に関するルールと違反にならないための確認ポイントをお伝えします。
最低賃金を下回るなんてありえない
「一生懸命働いたのに、生活ができない」なんてことはあってはなりません。労働基準法が「労働者を保護する」ためのルールの一つとして定めているが最低賃金です(具体的なルールは最低賃金法に定めています)。
たとえ、高校生のアルバイトであっても、最低賃金を下回ってはいけません。飲食店などで見かける「入社後100時間は見習いマイナス50円」のような求人表記ですが、見習い期間の給与を定めるのはOKですが、たとえ見習いといっても最低賃金を下回る給与はNGです。大手企業ではやりませんが、小さい居酒屋などでは平然と違反しているのが実態でしょう。
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています
神奈川県における最低賃金額の推移
冒頭でお伝えした通り、10月からの神奈川県における最低賃金は1225円となります。直近10年間の推移は、下表のとおりですが、注目すべきは「上昇率」です。
2022年2.98% → 2023年3.83% → 2024年4.49% → 2025年5.42% と急上昇となっています。
コンビニおにぎり🍙「最近高いな~」「昔の100円セールがなつかしい」と感じるくらい値上げが止まりませんが、そうした物価上昇に追いつけ、追い越せを目指しているのが賃金の上昇です。
| 年 | 時間額 | 増加額 | 上昇率 |
| 2015 | 905円 | 18円 | 2.03% |
| 2016 | 930円 | 25円 | 2.76% |
| 2017 | 956円 | 26円 | 2.80% |
| 2018 | 983円 | 27円 | 2.82% |
| 2019 | 1,011円 | 28円 | 2.85% |
| 2020 | 1,012円 | 1円 | 0.10% |
| 2021 | 1,040円 | 28円 | 2.77% |
| 2022 | 1,071円 | 31円 | 2.98% |
| 2023 | 1,112円 | 41円 | 3.83% |
| 2024 | 1,162円 | 50円 | 4.49% |
| 2025 | 1,225円 | 63円 | 5.42% |
労働基準監督署の立ち入りと最低賃金調査の実務ポイント
立ち入りのきっかけ
過去に勤めていた勤務先での経験です。朝9時か10時に、「○○労働基準監督署の方がお越しです」と受付から内線が入りました。突然の訪問に部署内は騒然、ひとまず受付に行き応対する者、会議室を確保する者、上長に報告する者など・・・
労働基準監督官は「ご挨拶」と言いながら、アポなしの事業所立ち入り調査に来たとのでした。
このような「アポなし」ということは稀なケースで、多くは1~2週間前に電話での事前連絡があるものです。
定期監督:全国的・地域的なテーマで一斉に実施(例:最低賃金改定直後)
申告監督:労働者からの申告や匿名通報
定期監督では労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法に関する基本事項を満遍なく(広く浅く)点検しています。
立ち入る事業所をどのように選定しているか不明ですが、飲食・小売・介護など違反が多い業種に重点実施しているようです。
申告監督については、労働者からの申告、相談によるもの(いわゆる「タレコミ」)で、「残業代が少ない」「長時間労働をしている」などの申告内容の実態を点検し、関係者(人事担当者や申告者と年齢や職務が近い労働者)へのヒアリングです。
最低賃金法に関わる調査内容
最低賃金違反が疑われる場合、以下の資料の提示を求められることが多いです。
- 賃金台帳(労基法108条)
- 出勤簿やタイムカード
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 賃金規程や給与計算方法の説明
ポイント
最低賃金の比較は、基本給だけでなく各種手当の扱いを正しく判断する必要があります。
算入できない:通勤手当、時間外手当、臨時の賞与など
算入できる:基本給、固定的手当(職務手当など)
最低賃金違反でよくあるパターン
『間違えだと分かっていて是正しない』ケースは少ないでしょう(何かと言い訳をして対応しないケースもあるかもしれませんが)。
何年も同じように給与計算をしていると、「間違えに気が付かない」「正しい計算式だと誤認識している」ことがあります。
是非、以下の1~6のよくある違反パターンを参考に、年度改定前(8〜9月)に全従業員の時間単価を棚卸して、最低賃金法違反になっていないか、総点検をお願いします。
1. 固定残業代込みで最低賃金を下回るケース
- 典型例
月給制の社員に「基本給+固定残業代」を支払っているが、実際の労働時間で時給換算すると最低賃金を下回る。 - 原因
固定残業代を基本給に上乗せして時給換算してしまう誤り(本来は固定残業代を除外して計算)。 - ポイント
固定残業代制度は要件が厳格で、計算上最低賃金を下回ると違反。
2. 無償または低額の研修・試用期間
- 。典型例
「試用期間は○○円/時」として本採用より低い時給を設定し、それが最低賃金を下回る。あるいは「研修期間は無給」。 - 原因
試用・研修期間も労働契約が成立している限り最低賃金が適用。 - ポイント
採用初日から最低賃金以上の支払いが必要。
3. 控除額が多すぎるケース
- 典型例
寮費・制服代・道具代などを給与から天引きし、手取りが最低賃金を下回る。 - 原因
控除項目の取り扱いを誤解している。 - ポイント
控除後の額で判断するわけではないが、不当に高額な控除は労基署から是正指導されやすい。
4. 所定労働時間の過小設定
- 典型例
月給制で所定労働時間を短く設定しているが、実態はもっと長く働かせているため時給換算で下回る。 - 原因
実労働時間で計算せず、名目上の所定時間で計算してしまう。 - ポイント
残業代未払いとセットで指摘されることが多い。
5. 時間外・休日・深夜割増を含めて計算してしまう
- 典型例
基本給が最低賃金以下でも、「残業代を入れたら超えているからOK」と誤解する。 - 原因
割増賃金は最低賃金計算に含められないことを理解していない。 - ポイント
割増分は別枠、純粋な所定内賃金で判定。
6. タイムカードと賃金台帳の不一致
ポイント
労基署は必ずタイムカードや勤怠記録と突き合わせる。
典型例
タイムカードでは月160時間勤務しているが、賃金台帳では140時間で計算している。
原因
労働時間管理の不備や、意図的な時間カット。
最低賃金上昇への医療機関の対応策
医療機関の場合、診療報酬は公定価格であり、一般企業のように価格転嫁ができないため、最低賃金の上昇は直接的に経営圧迫につながります。
このような環境では「人件費の総額を抑えつつ、サービス品質を維持・向上する」ための工夫が重要になります。
1. 業務の効率化とタスクシフト
- 医師や看護師が行っている業務のうち、資格不要なものを医療事務や看護補助者に移管(タスクシフト)
- 例:医療事務による問診補助、書類作成、看護補助者によるベッドメイキング、患者移送
- 同一労働時間でより多くの業務をこなせるようにすることで、採用人数の抑制が可能
2. ICT・デジタルツールの導入
- 電子カルテのテンプレート化や音声入力機能で記録時間を短縮
- 予約管理システムやオンライン問診を導入して受付・待ち時間を減らす
- 在宅勤務可能な事務業務(レセプト点検、集計など)を外部委託化することで院内人員を最適化
3. 勤務シフトの最適化
- 患者数の波に合わせた短時間勤務やパートタイム活用
- 平日午後や土曜午前など繁忙時間帯に集中配置
- 人員の多すぎる時間帯を削減し、総労働時間を調整
4. 人材の多能工化
- 医療事務スタッフが簡易な診療補助や物品管理を担当できるよう研修
- 看護補助者が清掃・備品発注も担当
- 1人が複数業務をこなせる体制で人員を削減
5. 福利厚生・やりがいで離職防止
- 賃上げが難しい場合でも、シフトの柔軟性や有休取得率向上、資格取得支援などで定着率を高める
- 離職率低下=採用コスト・教育コスト削減につながる
6. 補助金・助成金の活用
- 地方自治体独自の医療機関支援補助金
- 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入、労働時間短縮のための設備投資)
- IT導入補助金(予約システム、勤怠管理システム)
- キャリアアップ助成金(非正規職員の正規化)
小さな確認が、大きな安心に。
最低賃金の引上げは経営にとって負担でもありますが、同時に職場の魅力を高めるチャンスでもあります。
「法律で決まっているから」守るだけのものではなく、働く人と事業を支える大切なルールです。毎年の改定に合わせて見直すことで、安心して働ける職場づくりにもつながります。
「今の経営状況で賃上げは難しい!」とお考えの経営者のみなさま、人事責任者のみなさま、ぜひ一度社会保険労務士事務所ベイプラスにご相談ください。
★最低賃金について、さらに詳しく知りたい方はぜひ厚生労働省のホームページをご確認ください。