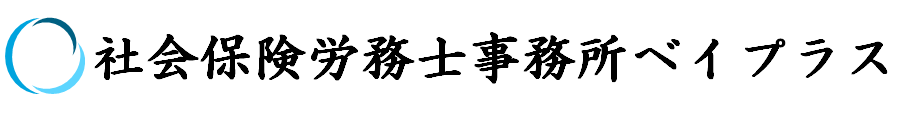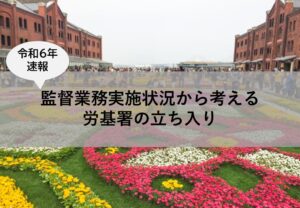【続編】労基署はここを見る!申告監督の調査項目と重要判例
先週のコラムでは、令和6年の監督業務実施状況の速報をもとに、労働基準監督署(労基署)の調査(立入監督)の傾向について解説いたしました。今回はその続編として、労働者からの申告によって行われる「申告監督」に焦点を当て、具体的にどのような項目が調査され、企業はどのような法的リスクに注意すべきかを、重要な判例を交えながら詳しく解説します。
従業員等から申告に基づく申告監督の状況
労働基準法は「労働者を保護する」もの。とこれまでのコラムでお話してきましたが、労働者と使用者は対等な関係とは言えず、労働者が弱い立場にあることが多く見られます。「人事部門に相談しても対応してくれない!」「法律違反じゃないの?!」と疑念があったときの相談先が「労働基準監督署」です。
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
「申告」は労働者にとって重要な権利であり、医療機関で働くみなさんにおいても例外ではありません。監督業務実施状況の速報による令和6年の医療保健業における申告状況については、以下の通りです。
申告監督は、労働者の具体的な訴えから始まるため、労基署も問題意識を持って調査に臨みます。今回ご紹介する調査項目や判例は、日々の労務管理における最低限のチェックポイントです。
要処理申告事業場1,297(前年1,154/前年比+143)
実施事業場903(前年863/前年比+40)
違反事業場621(前年577/前年比+44)
比率68.8%(前年66.9/前年比+1.9%)
賃金不払い 874事業所
被申告事業所(従業員等から申告を受けた事業所)において最も多い申告理由は「賃金の不払い」です。これは医療保健業に限らず、全業種において最も多い理由でした。
・給与(基本給・時間外手当・その他手当)が決められた支給日に支給されていない、あるいは遅配している。
・給与のうち、変動項目(時間外手当や夜勤手当など実績に応じて支給するもの)が支給されない。
・賃金規程で定められた計算通りに支給されない(一部カットしている)。
たとえ経営不振や資金繰り悪化であっても、毎月の給与は生活の基礎であることを考えると、労働者にとっては許されるはなしではありません。
解雇 138事業所
解雇は簡単ではありません。根拠である労働契約法第16条をみると、サラッと書いてあるのであまり印象に残らないかもしれませんが、労働者を保護するうえで、もっと重要なことは「解雇」です。映画などで「お前はクビだ!明日から来るな!!」ようなセリフを聞いたことがあるかもしれませんが、現実世界(特に「日本」)においてはまずありえないことでしょう。
とは言え、解雇に関する申告は多くあり、労務相談においても「”院長がカッとなって””その場のはずみで”『解雇』と言われた」事例があるのも事実でしょう。
労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
最低賃金 60事業所
アルバイトなどでは「時給制」であることが多く、最低賃金を下回っているかどうかは簡単にわかりますが、なかには「見習い100時間はマイナス50円」のような求人広告があります。飲食店に多く見られますが、試用期間として一定の勤務時間(勤務期間)は本来よりも低い賃金で雇うということは構いません。しかしながら、たとえ試用期間と言っても、その地域で定められた最低賃金は下回ってはいけません。
ちなみに神奈川県においては時給1,225円となります(令和7年10月4日より)。
申告監督で重点的に調査される項目
申告監督は、労働者からの「労働基準法に違反している」という具体的な申告に基づいて行われるため、調査のポイントは明確です。主に以下の項目が厳しくチェックされます。
1. 労働時間・休憩・休日
労働者からの申告で最も多いのが、労働時間に関するものです。
- 調査項目
- 労働時間の実態把握:タイムカード、PCのログ、メールの送信履歴、入退室記録など、客観的な記録と自己申告に乖離がないか。
- 時間外・休日労働:36協定が適切に締結・届出され、その上限時間を超える労働がないか。
- 休憩時間:法定の休憩(6時間超で45分、8時間超で1時間)が勤務時間の途中で適切に付与されているか。
- 管理監督者の範囲:役職名だけでなく、職務内容、権限、待遇の実態から見て、労働基準法上の「管理監督者」に該当するか。
2. 割増賃金
労働時間と密接に関連するのが、残業代などの割増賃金の支払いです。
- 調査項目
- 割増賃金の計算:法定の割増率(時間外、休日、深夜)で正しく計算されているか。計算の基礎となる賃金から除外できる手当の扱いは適切か。
- 固定残業代(みなし残業代)の有効性:基本給と固定残業代部分が明確に区分され、固定残業時間を超えた場合は追加で差額を支払っているか。
- 未払い賃金の有無:いわゆる「サービス残業」が発生していないか。
3. 解雇・退職
解雇に関するトラブルも、申告監督の引き金となりやすい項目です。
- 調査項目
- 解雇理由の正当性:就業規則上の解雇事由に該当し、かつ客観的に合理的で社会通念上相当な理由があるか。
- 解雇手続きの妥当性:解雇予告(30日前)または解雇予告手当の支払いが適切に行われているか。
調査項目から学ぶ、企業が知るべき重要判例
上記の調査項目は、過去の多くの労働裁判の積み重ねによって、その判断基準が形成されてきました。ここでは、実務に特に影響の大きい代表的な判例を3つご紹介します。
1. 労働時間に関する判例:【三菱重工業長崎造船所事件】
この判例は、「労働時間とは何か」という根本的な問いに対する最高裁の判断を示したものです。
- 事件の概要 造船所の従業員が、作業服や保護具の装着、準備体操、後片付けなどの時間が労働時間に含まれるとして、その時間分の賃金を請求しました。
- 判決のポイント 最高裁は、「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」と定義しました。その上で、作業服等の装着が事業所内で行うことを義務付けられていた実態から、これらの時間も使用者の指揮命令下にある「労働時間」に該当すると判断しました。
- 企業への教訓 タイムカードの打刻時間だけでなく、始業前の朝礼や準備、終業後の片付けなども、会社が義務付けていれば労働時間と見なされます。これらの時間を労働時間として扱わず、賃金を支払っていない場合、賃金未払いとして是正勧告の対象となる可能性があります。
2. 固定残業代に関する判例:【テックジャパン事件】
固定残業代(みなし残業代)制度を導入している企業は多いですが、その有効性が争われるケースは後を絶ちません。この判例は、有効とされるための要件を明確にしました。
- 事件の概要 「営業手当」が時間外労働の対価であるとして支払われていたが、何時間分の残業代に当たるのかが明確でなく、実際の残業時間に対する追加の支払いもなかったため、その有効性が争われました。
- 判決のポイント 最高裁は、固定残業代が有効とされるためには、
- 通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる部分が明確に判別できること
- 固定残業代を超える時間外労働が行われた場合、差額を支払うことが合意されていること が必要であると示しました。
- 企業への教訓 「基本給〇〇万円(〇時間分の固定残業代〇円を含む)」のように、金額と時間数を雇用契約書や賃金規程で明示する必要があります。「営業手当」や「役職手当」などの名目で支払うだけでは、残業代の支払いとは認められないリスクが非常に高いと言えます。
3. 解雇の有効性に関する判例:【高知放送事件】
普通解雇の有効性について、厳格な判断基準を示したリーディングケースです。
- 事件の概要 アナウンサーが2週間に2回寝坊し、ニュース放送を中断させる放送事故を起こしたことを理由に解雇されたことの有効性が争われました。
- 判決のポイント 最高裁は、「普通解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効になる」という「解雇権濫用法理」を示しました。本件では、過去の勤務成績は良好であったことなどを考慮し、解雇は重きに失するとして無効と判断しました。
- 企業への教訓 従業員に問題行動があったとしても、一度の失敗や能力不足を理由に即座に解雇することは、無効と判断される可能性が高いです。解雇を選択する前に、注意・指導や、研修、配置転換など、企業として解雇を回避するための努力を尽くしたかが厳しく問われます。
経営者の皆様へ ―「守りの労務管理」は最強の経営戦略です
経営者の皆様は、日々、会社の成長と発展のために尽力されていることと存じます。その中で、労務管理は後回しになりがちな、あるいは「コスト」として捉えられがちな分野かもしれません。
しかし、労基署の調査、特に今回ご説明した「申告監督」は、たった一人の従業員の「なぜ?」という疑問や不満から始まります。
本日ご紹介した数々の判例は、決して過去の他人事ではありません。これらは、自社でも起こりうる現実的な経営リスクを示しています。ひとたび労務トラブルが発生すれば、未払い賃金の支払いや訴訟対応だけでなく、他の従業員の士気低下、企業の社会的信用の失墜など、計り知れないダメージを受ける可能性があります。
「守りの労務管理」を徹底することは、単に法律違反のリスクを回避するためだけのものではありません。それは、従業員が安心して能力を発揮できる職場環境を整え、無用な紛争を未然に防ぎ、結果として企業の生産性を高めるための『未来への投資』です。
就業規則の整備、労働時間の適正な把握、明確な賃金制度の構築。これらは、会社を守り、ひいては従業員とその家族の生活をも守る、経営の根幹と言えます。
「うちは大丈夫」と思っていても、法律や判例のトレンドは常に変化しています。この機会に、専門家の視点で自社の労務管理体制を一度「健康診断」してみませんか。社会保険労務士事務所ベイプラスでは、経営者と従業員のみなさまが本業に安心して集中できる、盤石な経営基盤づくりを全力でサポートいたします。