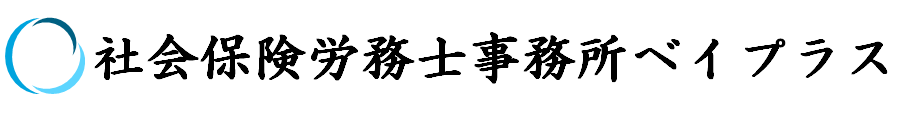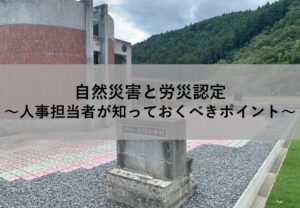監督業務実施状況(令和6年速報)から考える労基署の立ち入り
「税務調査が来た!」と経営者にとって非常にドキドキする、嫌な仕事かもしれません。法人が申告した法人税や消費税に誤りがないか、定期的に点検するのが税務調査で、税務署が行う重要な業務です。これと同じように労働基準法や労働安全衛生法などが遵守されているか点検するのが「労働基準監督署(以下、労基署)」よる『監督』です。
経営者としては、今まで労働者の誰からも苦情が出ていなかったのに、「なぜ労基署が来るのか」、「なぜこのような指摘を受けなければならないのか」と思うかもしれません。
それは、今、労働者から何ら不満の声がないだけで、必ずしも満足して働いているわけではないかもしれません。
労働者が労基署に駆け込む前に、「自社を見直す貴重な機会」としてとらえ、客観的に指導してもらうことで「将来を良くする」ように考えるきっかけにしていただけると幸いです。
労働基準監督年報(監督業務実施状況)とは
厚生労働省は、令和6年の監督業務実施状況の速報を取りまとめました。
14万2477事業場を対象に定期監督等を実施し、70.1%に当たる9万9906事業場で労働基準法や労働安全衛生法などの法令違反を確認。違反率・違反事業場数ともに前年を上回っている。労働時間や割増賃金違反などによる送検事案も増加しました。
令和6年の違反事業場数は、9万6831事業場(違反率69.6%)だった前年より3075事業場増えました。
こうしたデータは『労働基準監督年報』(速報として「監督業務実施状況」)が発表されます。前年1月~12月における全国の労基署において実施した立ち入り調査(「監督」といいます)の結果を集計したものです。
労基署の立ち入り調査とは
定期監督
違反が予想される業種などから、管轄内の事業所を選定して実施するものです。令和6年においては14万2477事業所に調査がありました。定期監督の多くは、労基署から調査の通知が郵送され、指定する日時に労働基準監督官という労基署の職員が事業所を訪れます。
ごく稀に、事前の通知なく、事業所にくる、「立ち入り調査」が行われることがあります。筆者の経験では当日朝9時ころに”ご挨拶”と言いながら事業所を訪問し、調査したい旨を伝え、12時~13時くらいまで、会議室を使って調査したことがあります。
申告監督
「従業員が・労基署に・申告した」これがスタートとなります。労基署では従業員が持参した出勤簿や給与明細、本人からの説明により、法律違反が考えられる場合には、事業所に調査に入ります。事前に「来所依頼」として通知文書が届き、来所日時や用意してほしい資料などが示されています。申告した従業員がわかる場合と氏名等を伏せて分からない場合があります。当日は、労働基準監督官が資料の確認や従業員(申告した方と同年代・同じ職種)に対してヒアリングを行います。
なぜ労基署は調査するのか
理由の一つとして「過重労働(過労死)」の防止があります。生活するために働くことは大切ですが、長時間労働が続けば健康を害することがあります。会社として利益の追求は重要ですが、多くの人の命を削ってまでも得るものではありません。
長時間労働による脳・心臓疾患の罹患、精神障害を患ったことによる過労自殺など、人の命を守ることも行政(=労基署)の重要な役割です。調査を受けて喜ぶ経営者はいませんが、労働者と大きなトラブルになる前に、是正するきっかけが労基署の調査となります。
定期監督結果から見る医療保健業におけるポイント
監督業務実施状況は1号から17号の業種別に集計されており、病院やクリニックは「13号医療保健業」に該当します。 医療保健業の集計結果は以下の通りで、定期監督を受けた事業場、違反事業場は前年より増えた結果となっています。
〇定期監督実施事業場 3,354(前年3,121/前年比+233)
〇違反事業場 2,357(前年2,053/前年比+304)
〇比率 70.3%(前年65.8%/前年比+4.5%)
ポイントはどのような違反があったのか、法律別の違反状況について、ランキング形式で見ていきます。
労働基準法関係
1位 32条 労働時間(698件)
昨今の「働き方改革」の中心が、労働時間の管理、長時間労働の抑制で、2位の割増賃金とセットで考えていただきたい内容です。
労働基準法の基本事項ですが、1日8時間以上働かしてはいけません。これを基本として知っておかないと、「どのくらい働かせると長時間労働になる?」「なぜ割増賃金が発生するの?」ということが理解できません。当たり前のことですが、実は当たり前を知らない従業員は多くいます。
労働時間に関するの多くは、時間外・休日労働に関する時間の制限超過、労使協定(=「36(サブロク)協定」)の未届けによるものです。残業の多い事業所が短縮させることは簡単ではありませんが、いつまで改善されないようだと、事業の継続は困難になります。経営者が率先して改善に努めましょう。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
2位 37条 割増賃金(675件)
1位の労働時間に合わせて点検される項目です。無作為に抽出した数名の労働者をサンプルとして「出勤簿」と「賃金台帳」をセットで調査します。出勤簿に残業時間が計上されているのに、賃金台帳の金額を見ると正しい賃金になっていないことがあります。「昔からこの計算式でやっていた」なんてことがあると、正しい計算式で再計算され、『不足額●ヶ月分を支払いなさい』という是正勧告が出されます。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
3位 15条 労働条件の明示(526件)
4位 就業規則とセットで考えていただきたい内容です。
小規模な会社ではそもそも就業規則がない、労働条件通知書も交付していないことが多くあります。労働条件通知書は、労働者が労基署に申告した際に確認する基本事項です。
「常勤や正社員などの正規労働者は雇用契約書を締結しているけど、アルバイトなどの非正規労働者は口頭説明のみ。賃金は払っているから問題ないでしょ?」なんて声を聞くこともありますが、非正規であってもしっかりと書面を作成して、労働条件を明示することが基本です。(なお、紙の交付に代わり、スマホ等で確認できる電磁的記録でもOK)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
4位 89条 就業規則(450件)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
5位 39条 年次有給休暇(377件)
「年休を取得させない」、「年休と認めず欠勤扱いにする(=給与を減額する)」などの違反です。年休は労働者に認められた権利であり、いつ取得するかも労働者の自由となります。
よく聞くのは、「事業の正常な運営を妨げる場合、労働者に時期の変更を求めることができるから取得日を変更させた!」という事例ですが、この「妨げる」と判断されるハードルは非常に高く、使用者による取得時期の変更権は容易でありません。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
6位 108条 賃金台帳(279件)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
その他 労規則24条の7 年次有給休暇管理簿(212件)
第二十四条の七 使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない
5位の年次有給休暇とセットで考えましょう。いつ付与したから、何日付与したのか、いつ・何時間取得したのかをまとめた個別表です。年休は取得時効の都合で、2年間取得可能ですので、前年の繰り越し分も含めて、エクセルにまとめておけば十分です。
ただし、人数が増えれば増えるほど煩雑ではありますので、10名程度を超える(もしくは超えそう)事業所であれば、勤怠管理システムを導入し、システム上で管理することをお勧めします。
労働安全衛生法関係
1位 66条 健康診断(761件)
労働安全衛生法関係でもっとも多かったのは、健康診断に関する違反です。年に1回の定期健康診断はどの業種でも必須のことですが、これに加え、医療機関においては電離放射線健康診断など特殊健康診断を半年に1回実施することになっています。放射線業務に従事する医師や放射線技師、看護師ですね。また、有機溶剤などの取り扱う医師や臨床検査技師も対象となります。
従業員が50名を超える事業所においては、産業医を選任し、健康診断の結果をもとに就労の可否(検査結果によっては就労制限してもらうことも)を記録しましょう。労基署への提出もお忘れなく。
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
2位 17条~19条 衛生委員会関連(200件)
2位と4位は衛生委員会の開催と衛生管理者の選任です。これはセットで取り組む必要があります。医療機関の場合、医師が衛生管理者として登録できますが、看護師や事務員にも衛生管理者の資格取得が望ましいです。衛生管理者の役割には院内の巡視があり、毎週1回取り組むことを基本としています。忙しい医師が、毎週お手洗いや診察室の点検なんて、難しいですよね。
また、衛生委員会では衛生管理者の巡視結果から労働環境の改善に向けた検討も必要です。ストレスチェックの実施検討も衛生委員会の重要な役割となっています。
いずれも50名を超える規模の事業所が適用となるため、50名に満たない事業所では取り組む義務はありません。しかしながら、汚いお手洗いや診察室は、来院する患者さんにも働く従業員にとって良くないですねよ。日頃当たり前にやっている衛生管理が、実は法律上、重要なことだったりします。たとえ小規模な事業所でも、衛生管理は大切にしましょう。
第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
3位 66条の8の3 時間把握(222件)
第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
4位 12条 衛生管理者(177件)
2位「衛生委員会」を参照してください。
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
働きやすい職場をつくることで、従業員の定着率向上や医療の質の安定化につながります
今回の労基署データから明らかになったのは、医療・保健業界における労務違反の多くが、長時間労働や未払い残業代、労働時間管理の不備といった基本的な問題であるということです。
これらは放置すれば、労基署からの是正勧告や企業名公表にとどまらず、訴訟リスクや人材流出にも直結します。経営の持続可能性を脅かす要因となりかねません。
一方で、逆にいえばこれは仕組みを整えれば改善可能な課題です。労務コンプライアンスを強化することは、単なる法令遵守にとどまらず、職員の定着率向上や医療の質の安定化にもつながります。
労基署の監督を「取り締まり」ではなく、経営改善のチャンスと捉え、今こそ自院の労務管理体制を点検することが求められています。
これまで調査の経験がない事業所や過去の調査から3年以上経過している場合は、いつでも調査を受けられるように自主点検を進めましょう。社会保険労務士事務所ベイプラスでは、自主点検のご支援、調査の立ち合い、是正対応についてサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
【次回予告!】従業員等から申告に基づく申告監督の状況について
次回は、従業員からの申告に基づく「申告監督」について詳しく解説。医療保健業においては、いずれも前年を上回る結果となっています。
(参考)
要処理申告事業場1,297(前年1,154/前年比+143)
実施事業場903(前年863/前年比+40)
違反事業場621(前年577/前年比+44)
比率68.8%(前年66.9/前年比+1.9%)