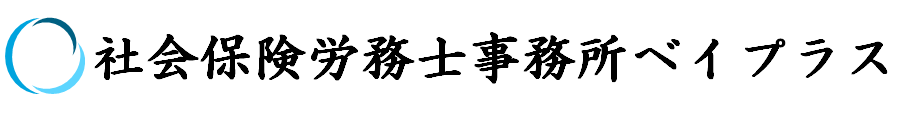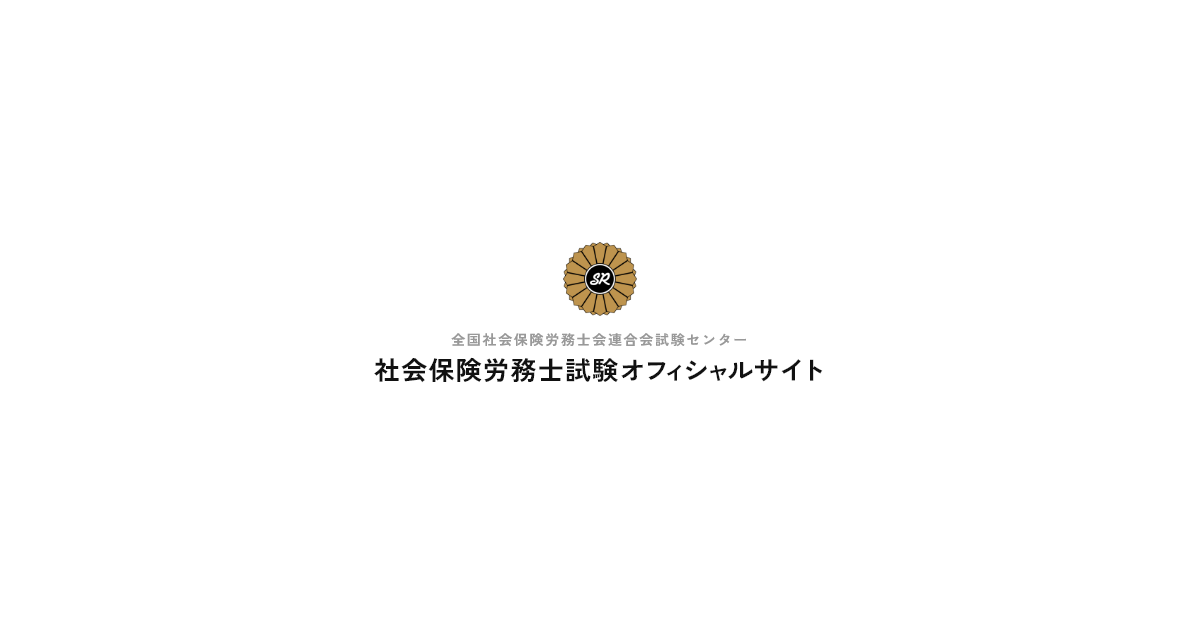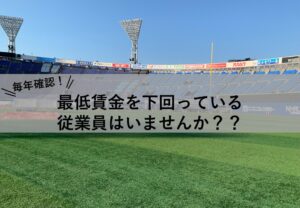【社会保険労務士試験】焦る気持ちを得点に変える「選択と集中」の直前戦略
8月の社労士試験が近づき、「思うように勉強が進んでいない」「今から何をすればいいか分からない」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
予備校の先生たちからは“合格するための”メッセージがたくさんあり、「あまり勉強できていない」「このままじゃ合格は難しい」と感じている方にはなかなか届かないと思います。
そう感じている方々に向けて、私のコラムでは少々違った視点で、お話をしたいと思います。
お伝えしたいことは、『成果を持って試験を終えることは、来年の大きなアドバンテージになる』です。
すべての科目をやろうとしない
直前期に陥りがちなミスは、「まんべんなく全科目を復習しよう」とすること。これは一見よさそうに見えて、結果として「どれも中途半端に終わる」リスクがあります。
この時期は、焦ってすべての科目に手を広げるのではなく、「選択と集中」で“確実に点を取れる場所”を見極めることが重要です。
「これは取れる」と思える科目に絞って点数を積み重ねること。
特に、科目別の得意・不得意や、選択式/択一式の配点バランスを考えながら、狙うべきポイントを決めましょう。
このコラムでは、しっかりと固めれば得点源になる『年金科目(厚生年金・国民年金)』とコスパの良い『徴収法』について見ていきます。
厚生年金・国民年金は得点源になる!
出題が安定している
両科目とも、例年、保険者・被保険者の定義、資格取得・喪失、年金の種類、給付要件などが出題されており、パターンが比較的読みやすい分野です。
予備校のテキストは大変分かりやすく整理されていますが、なかには全体像が理解できていない論点もあるかもしれません。
基本事項が理解ができていないときは「一般人向けの資料」を見てみることが近道だったりします。
日本年金機構では一般の方向けに優しく、分かりやすいパンフレットを作成しています。
「社労士試験の受験生であれば知っていて当たり前」と言われるかもしれませんが、テキストとは違った視点で、全体像を理解するにはオススメです。
表や図で整理できる
年金額や支給要件などは、表にまとめて整理することで、数字や条件が頭に入りやすくなります。受験生の多くが苦手とする分野ですが、逆に言えば差をつけやすいということでもあります。
厚年・国年は情報量も多く、条文の表現も抽象的なため、初学者が直前に完璧を目指すと逆に混乱することもあります。
したがって、学習歴に応じて目標を変えることが大切です。
法改正は予備校テキストで確実に抑える
年金科目は毎年法改正があり、過去3年~5年の改正点は確実に理解しておくことが必要です。
予備校では法改正に対応したテキスト、特別講座を実施しているため、以下のポイントを押さえながら振り返っておくことも有効です。
・条文ベースの理解を強化:「○月以内に」「○年分まで」など数字の正確性を問う問題が多いため、暗記でなく根拠を意識。
・併給・支給停止の構造理解:老齢・障害・遺族年金の併給可否や、支給停止の条件はパターンで整理して覚えると得点源に。
・改正部分は出題者の狙い目:条文の変更箇所は“出題者の出したい場所”と心得る。特に新制度(在職定時改定など)を丁寧に。
・数字・時期・金額の正確さ:受験生の差が出るのは細かい数字の記憶(例:報酬比例部分=平均標準報酬月額×5.481/1000など)
徴収法も“得点源”になる!
出題範囲が狭く、学習効果が出やすい
徴収法は、他の科目と比べて出題範囲が狭く、本試験で問われるポイントがある程度決まっているため、短期間でも集中して学習すれば点が取りやすい科目です。
徴収法では「概算保険料はいつまでに納付?」「確定保険料の申告期限は?」など、具体的な期日や割合の暗記が求められます。
一見面倒に感じますが、数字は覚えてしまえばブレが少ないため、他の受験者と差をつけやすいポイントです。
“細かい論点”は後回しに
徴収法も、満点を狙いにいくと「印紙保険料の特例的な扱い」や「一括有期事業の例外規定」など、細かく難解な論点に入り込んでしまいがちです。
そこで、直前期の学習では優先順位をつけて取り組むのはどうでしょうか。
- 「高」:概算・確定保険料の仕組み、納期限、申告の時期
- 「中」:成立/消滅の手続き、継続事業・有期事業の違い
- 「低」:印紙保険料、特例措置、徴収法独特の例外条文など
今年を“来年につなげる”と考える
直前期は、不安や焦りが大きくなる時期です。しかし、だからこそ「今できること」を明確にし、得点に変えていく姿勢が大切です。
仮に今年、全科目の完成が間に合わなかったとしても、「厚年・国年だけは得意になった!」という成果を持って試験を終えることは、来年の大きなアドバンテージになります。
社労士試験は、知識の積み上げが武器になる試験です。
焦らず、でも確実に、「点が取れる場所」から着実に固めていきましょう。
厚生年金・国民年金は、一度基礎を理解すれば強力な得点源になります。今からでも遅くありません。
自分にとっての“勝ち筋”を見つけ、1点でも多く積み上げていきましょう。
応援しています!